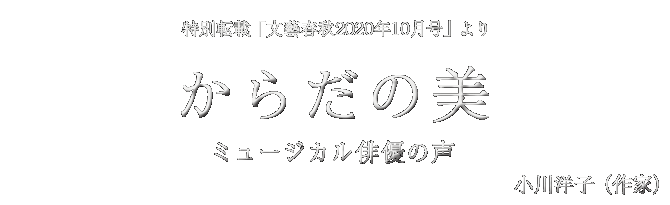人はなぜ歌うのか。
学問的にははっきりした答えは出ていないらしいが、この疑問自体が、美しい詩の一行のように心に深く響いてくる。
人間は歌う生きものだ。子どもを寝かしつける、蝋燭を立てたケーキで誕生日のお祝いをする、表彰台の真ん中に立つ勝者を称える。いろいろな場面に歌が登場する。楽しければハミングをし、音楽の時間には合唱をし、カラオケボックスに籠ってお金を払ってでも歌おうとする。なぜそうするのかよく分からないままに、気づけば声の音楽を口から発している。
赤ん坊を見ていると、泣き声が既に歌だと分かる。喉を開き、胸を膨らませ、自らの声を他者に届けようとする。抑揚もあればリズムもある。たとえ生理的な欲求であっ多としても、自分の思いを伝えたいという気持ちがあふれ出ている。産声とともに生まれてくる人間は、やはり歌とは無縁でいられない運命を背負っているのかもしれない。
地上の歌うたいが人間であるならば、空中のそれは鳥だ。生物学的に言葉の起源を探るため、ジュウシマツの歌を研究している岡ノ谷一夫先生のご本を読むと、彼らが歌にどれほど健気な努力を注いでいるかが分かって興味深い。ジュウシマツのオスはメスに選んでもらうため、より複雑な歌を、長く、綺麗な声で歌おうとする。父親から教えてもらった歌を記憶し、アレンジしながら練習に励む。他の小鳥たちのさえずりに邪魔されない、自分だけの孤独な世界を確保し、技術の上達に務め、いざという時、つまり求愛の時に備えるのだ。上手な歌であればあるほど、それを聴いたメスの血中性ホルモンは増加するらしい。
歌が愛のやり取りに重要な役目を果たす事実は、人間にも当てはまる。平安貴族は恋しい人に和歌を贈り、ロック少年は、もてたいためにシャウトする。ただ、言葉を持たない小鳥たちの歌には、いわゆる意味はない。ジュウシマツのメスが受け取るのは、「愛している」という言葉ではなく、声が生み出す魅力だけだ。それだけでお互い、十分に心のやり取りをしている。
たいていの場合、人は言葉で歌う。しかし、本当に引き込まれている時、言葉の意味にはあまりとらわれていない。むしろ感動の渦の中では、頭で意味を考えるレベルを超越し、言葉と音が境目なく一つに溶け合い、純粋な響きの波になっている。つまり、理屈から解放された、より自由な状態に浸っている。
こうやって考えてみれば、オペラやミュージカルが生まれたのも自然の流れだと思える。声、というものがいかに豊かな感情を運んでくるか、人は本能的に知っていたに違いない。人間が自分たちの都合で作った、不自由で不完全な言葉だけではなく、偉大な何者かから授けられた声で世界を表現してみたい。そう願うのは当然だろう。
ミュージカル『レ・ミゼラブル』を観劇した際の衝撃は、今でも忘れられない。本当の意味で生身の人間の声に圧倒された、初めての体験だった。その時のジャン・バルジャン役は福井晶一。一旦声の魅力に取りつかれてしまったら、そこから逃れるのは難しい。目は自分の意思で閉じることができるが、耳は常に開かれている。知らないうちに声は耳をすり抜け、秘密の小部屋に眠る鼓膜を震わせ、胸を揺さぶってくる。まさに血中性ホルモンの濃度が上がったジュウシマツと、同じ状態である。
説明するまでもないが、ミュージカル『レ・ミゼラブル』はヴィクトル・ユゴーの小説を原作とし、十九世紀フランスを舞台に、罪悪、貧困、叶わぬ理想、すれ違う恋等々、さまざまな苦悩を背負った人々の姿が、全編歌によって描かれている。ある者は自らが信じる絶対的な正義に押しつぶされ、川に身を投げる。ある者は振り向いてもらえない人をひたすらに愛し、身代わりとなって銃弾に倒れる。幼い我が子に思いを残して病死する母もいれば、平等な社会を実現しようともがきながら報われない若者もいる。そしてジャン・バルジャンは、罪人としての過去を背負いつつ、血のつながらない娘、コゼットを慈しむことで、自分の命を神に捧げても誰かを守ろうとする、人間的な尊さに目覚めてゆく。
繰り返すようだが、このように繊細な内面の動きがすべて、歌で表現されているのだ。その歌を司っているのが声だ。動き、表情、照明、衣装、あらゆる表現を一つにつなげ、一人の人物を作り上げ、とうてい言葉では表しきれない何かを劇場に響かせる。もしかしたらそれは、魂と呼ぶべきものなのかもしれない。そこに、他のどんな芸術家にも真似できない造形美が生まれる。その場限り、一瞬で消えてゆく美だからこそ、いっそう愛おしい。
写真はプロローグ、仮釈放されて間もないジャン・バルジャンである。胸には囚人の焼印が見える。理不尽な社会の仕打ちにい嫌気がさし、司教館の銀食器を盗んだ彼は、罪を追及するどころか、更に銀の燭台を差し出してくる司教の教えに触れ、過去の自分を捨て去る決意をする。この場面で、『独白』が歌われる。看守の殴打ではなく、神の静かな手によって自らの愚かさに気づかされた彼は、動揺する。後悔にさいなまれる。なぜ自分だけがこんな目に逢うのか、という怒りは消えないままに、なぜ神は自分を救ったのか、自問する。舞台にはジャン・バルジャン一人きりだ。彼の心の声が次々とあふれ出てくる。観客は神と罪人の対話を目撃することになる。一人の人間が、何の道具にも頼らず声だけを使ってこれほどの場面を生み出している事実に、ただひれ伏すしかない。
福井晶一の声には品がある。信頼し、すべてを委ねられる包容力がある。『独白』の最後、黄色い仮出獄許可証を破るところ、福井晶一の声に包まれていると、これから先、バルジャンの人生に訪れるだろう光を、信じることができる。コゼットと出会い、彼女のために、自分を死なせてくださいと神に祈る彼の魂の輝きが、既に芽生えているのを感じる。声の先に希望がある。
人はなぜ歌うのか。答えは知りたくない気がする。詩の一行を暗唱するように、疑問をそのまま抱えておいた方が、より深く声の神秘に浸っていられるからだ。